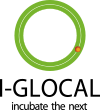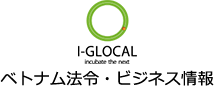日越VAT制度の違いと事業運営への影響
2025/10/15
- I-GLOCAL CO., LTD.
- 米国公認会計士
- 熊谷 克樹
はじめに
日本の消費税とベトナムの付加価値税(VAT)はどちらも物やサービスの取引にかかる税金であり、基本的な仕組みは似ている。しかし、その運用や手続には多くの違いが存在する。本レポートでは、①決済手段、②申告頻度、③納付方法、④還付の仕組み、⑤還付までの期間という5つのポイントで日本とベトナムの制度の違いを整理する。また、2025年7月施行の改正VAT法を踏まえ、業種ごとに留意すべき点もまとめた。ベトナムで事業を営む企業の税務手続や資金繰りに備える一助となれば幸いである。
日越VAT制度の主要な相違点(5項目)
日本の消費税とベトナムのVATの主な相違点を以下の5項目に沿ってまとめる。
| 項目 | 日本(消費税) | ベトナム(VAT) |
| 決済手段 | 現金・非現金いずれも可 | 500万VND以上の取引は非現金決済が必須 |
| 申告頻度 | 年1回の確定申告 | 月次または四半期ごとに申告 |
| 納付方法 | 前年度実績に基づく予定納付 | 申告対象期間に発生した税額を翌月に納付 |
| 還付の仕組み | 確定申告時に自動還付 | 別途申請が必要 |
| 還付までの期間 | 約2か月 | 数か月~数年(地域・時期・案件により大きく変動) |
以下、それぞれの項目について詳しく解説する。
1. 決済手段の違い(現金/非現金要件)
日本では、消費税の控除に際して支払い手段に制限はなく、現金・非現金いずれの決済でも控除可能である。一方、ベトナムでは非現金決済が原則であり、特に取引金額が500万VND(約3万円)以上の場合、銀行振込など非現金手段での支払いが控除要件となっている。これは、正規のVATインボイスに加え、銀行送金記録などの証憑がなければ仕入税額控除が認められない運用を反映したものである。また、適切なVATインボイスを取得していない場合や、インボイス上の社名誤記といった不備がある場合には、控除が否認される可能性が高い。したがって、ベトナムでは取引の都度インボイスの内容を確認し、非現金決済を徹底することが求められる。
※補足:従来は、非現金決済が必要となる取引金額は2,000万VND(約12万円)以上とされていたが、法改正により、VAT込み500万VND(約3万円)以上に引き下げられた。
2. 申告頻度の違い(年次申告 vs 月次/四半期申告)
日本では原則として年1回、事業年度末に消費税の確定申告を行う。一方、ベトナムでは月次または四半期ごとに申告・納付が必要であり、新設後12ヵ月未満の企業や、前年度売上が500億VND(約3億円)未満の小規模企業は3ヵ月に一度の申告で済む が、それ以外の企業には毎月の申告が義務づけられている。
したがって、ベトナムでは月次ベースで取引を集計し速やかに申告書を作成する体制や、そのための人員確保が欠かせない。日本の感覚で年度末にまとめて対応しようとすると間に合わないため、現地の申告頻度に合わせた経理・税務スケジュールを組む必要がある。
3. 納付方法の違い(予定納税の有無等)
日本では、前年度の消費税額に応じて中間納付(予定納税)を行い、年度末に精算する仕組みとなっている。一方、ベトナムには予定納税の制度がなく、各月または四半期ごとに実績ベースでVATを算出し、翌月に納付する方式である。納税はその都度完結するため、常に最新の納税額を把握し、計画的に納税資金を確保しておく必要がある。特に資金繰りに余裕のない企業では、納税漏れを防ぐための内部管理体制の整備が重要となる。
4. 還付の仕組みの違い(自動還付 vs 要申請)
日本では、確定申告時に仕入税額が売上税額を上回ると、その差額は自動的に還付される。輸出取引が多い企業では、確定申告だけで還付が受けられるため、還付額を前提に資金計画を立てることも一般的である。
一方ベトナムでは、VAT申告だけでは還付は受けられず、別途還付申請と厳格な審査を経る必要がある。申請には契約書・インボイス・輸出入関連書類などの詳細資料が求められ、税務当局による実地調査や質問対応も避けられない。特に初回申請では税務調査(監査)が必ず実施されるのが通例であり、還付は当局の承認を要する特別な手続という位置づけである。
また、還付可能な条件も年々厳しくなっており、多くの企業では仕入超過分を次期へ繰り越して調整する対応が一般的となっている。ベトナムで還付を受けるハードルは高く、手続にも相応の時間と労力を要することを念頭に置く必要がある。
5. 還付までの期間の違い(迅速性 vs 長期化)
上記の制度面の違いにより、還付金の受け取りにかかる期間にも日越間で大きな差がある。日本では確定申告書を提出してから1~2か月程度で還付金が振り込まれるのが一般的である。一方、ベトナムでは還付申請後の審査に長い時間を要するケースが多く、還付までの所要期間は案件や地域によって数か月から数年と幅がある。例えば、現在ハノイ市では比較的短い場合で2~10か月程度で還付されるのに対し、ホーチミン市では2~3年を要する事例も少なくない。こうした所用期間はあくまで現時点での傾向であり、当局 の運用方針や担当官の対応によって地域・時期毎に大きく変動する可能性がある。そのため、ベトナムではVAT還付を前提とした資金計画は避け、保守的な予算編成が推奨されている。法令上は所定の期間内処理が謳われているものの、実務では担当官の裁量や追加資料要求などにより遅延が発生し、必ずしも法定どおりに還付されないのが現状である。ベトナムで事業を営む場合、VAT還付は時間を要する前提で資金繰りを検討することが肝要である。
業種別に見たVATの留意点
上記の一般的な違いに加え、業種ごとに注意すべきポイントが存在する。製造業、貿易業、サービス業の3つの業種について主な留意点を整理する。
- 製造業
工場設備や機械の導入など操業前の大型投資により多額の仕入VATが発生する場合、一定の条件を満たせば還付申請が可能である。従来は、投資フェーズでのVAT累計額が3億VNDを超えると還付申請が可能とされ、多くの企業がこの基準を目安に還付を行ってきた。しかし、改正VAT法により新たに「売上計上開始後1年以内」という申請期限が設けられた点に注意が必要である。たとえ還付額が基準額を超えていても、売上開始から1年を過ぎると還付申請ができなくなるリスクがある。これにより、従来のように還付の時期を柔軟に調整することが難しくなり、投資段階から計画的に申請スケジュールを立てる必要がある。また、改正VAT法では従来規定上不明瞭であった既存事業の生産能力向上や設備のアップグレードのような拡張投資に関するVAT還付も明確に認められることになった。増産投資に該当する場合は、適用の可否を専門家と確認しながら手続きを進めことが望ましい。
- 貿易業
商品の輸出入を扱う貿易業では、輸出取引が多いほど仕入VAT超過となりやすい。しかし改正VAT法により「輸入した商品をそのまま輸出する取引」については今後VAT還付が認められなくなった。これは、三国間取引など、単に商品を通過させるだけのビジネスモデルに対し還付を認めない方針への転換である。一方、保税区の企業(EPE)向けの販売は、引き続き還付対象となる。そのため、取引形態や販売先によってVATの負担状況は大きく異なり、価格設定や事業計画の見直しが不可欠である。
加えて、輸出取引では税率0%が適用される場合でも、適切な輸出証憑の提出求められる。書類不備によるリスクを避けるため、輸出入関連書類の管理体制を万全に整えておくことが重要である。
- サービス業
サービス事業では、提供先が国外の顧客や輸出加工企業(EPE)の場合、VAT0%が適用されるケースがある。従来は、会計・監査、事務所賃貸など幅広いサービスが「輸出サービス」として0%対象とされてきた。しかし、改正VAT法により、EPE向けサービスのうち製造活動に直接関与しないものは0%適用外と明確にされた。製造工程に直接関連しないサービスは今後課税対象となる可能性が高く、注意が必要である。もっとも、「直接関与するサービス」の範囲は明確に定義されておらず流動的なため、今後のガイドラインや通達を注視しつつ、契約条件(税抜価格か税込価格か等)を慎重に見直す必要があるだろう。
また、海外顧客向けサービスの提供については、そのサービスの提供地や消費地によってVATの扱いが変わる点も留意すべきである。電子サービスも含め、ベトナムでは課税対象とされる事例も増えており、日本国内の感覚で安易に0%免税取引と断定せず、取引ごとに適用税率やインボイス発行要件を個別に確認することが重要である。
おわりに
日本とベトナムのVAT制度の相違点を理解することは、ベトナムでの事業運営において税務コンプライアンスを確保し、キャッシュフロー上の不測の事態を回避するために不可欠である。特に、VAT還付をめぐる手続の複雑さや所要時間の長さは企業活動に大きな影響を及ぼしうるため、制度変更の動向も踏まえて慎重に対応したい。
今後もベトナム当局の運用は変化する可能性があり、実務上は担当官の裁量によって追加資料を求められるなど不確実性が残る。自社のリソースのみで対応が難しい場合は、最新動向に精通した会計・税務の専門家に相談しながら、適切なプロセス整備や申請手続きを進めることが、リスク軽減と信頼性確保の観点から推奨される。
関連レポートはこちら
本テーマに関連するレポートを以下で紹介しています。ぜひ、あわせてご覧ください。
・ベトナムの付加価値税(VAT)還付の概要と法改正による影響
・ベトナムの付加価値税(VAT)の概要と法改正の主要ポイント
・新投資プロジェクトに対する付加価値税(VAT)還付手続きの留意点