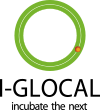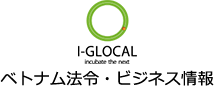近年のビジネス環境における労働契約書作成時の留意点
2025/06/20
- Le Que Ngan
はじめに
近年、デジタルトランスフォーメーションや新たな働き方の普及、情報セキュリティ要件の高まりなどにより、ビジネス環境は大きく変化している。このような状況下、雇用者は労働者との労働契約書の内容についても、法令を遵守しつつ、自社の利益を損なわないよう適宜見直すことが求められる。本稿では、雇用者が労働契約書を見直す際に重要となるポイントを整理する。
1. 新たな働き方のトレンドと労働契約への影響
テクノロジーの発展や働く人々の意識の変化により、従来のオフィス勤務という働き方は、少しずつより柔軟なスタイルへと移行しつつある。なかでも注目を集めているのが、リモートワーク(あるいはハイブリッドワーク)とフリーランスという二つの働き方である。これらにはそれぞれに特有の特徴があり、法的な明確さと実務上の運用可能性を確保するためには、締結する労働契約にもそれに応じた工夫や調整が必要となる。
1.1. リモートワーク
現行法においては「リモートワーク」という用語自体は明確に定義されていないが、一般的には「雇用者の管理する職場以外の場所、たとえば労働者の自宅などで完全または特定の日に労働契約に基づく業務を行う働き方」を指す。特にコロナ禍を経た現在では、フルリモートワークや出社との組み合わせは、社会全体で広がりを見せている。
このような働き方においても労働関係は引き続き有効であり、雇用者としては管理の透明性と業務運営の円滑さを確保するため、労働契約書の作成時に留意すべきポイントがある。
・勤務地の明確化:リモートワークの勤務対象となる場所の範囲は、労働契約書において明確に定める必要がある。たとえば、労働者の自宅など具体的な場所を記載する他、事前の通知および雇用者の同意があれば勤務場所を柔軟に変更できる旨を明記する方法も考えられる。なお、すでに社内で「リモートワーク」に関する就業規則や内規を設けている場合には、それらの内容を労働契約書で準用する形で対応することも可能である。
勤務場所を明確にしておくことにより、たとえば公共スペースなどの情報セキュリティ上のリスクが高い場所で業務を行われることを防ぐことができる。また、勤務中に事故等が発生した場合に、それが労働災害として認められるかどうかを判断する上でも勤務地の明確化は重要な要素となる。
・賃金・手当の見直し:労働法第95条第1項に基づき、雇用者は合意された賃金、労働生産性、および業務の成果に応じて労働者に賃金を支払うものとされている。ただし、各雇用者は自社で定めた賃金規程に基づき、賃金を支給しているのが実務上の運用である。そのため、労働者が「リモートワーク」へ移行した場合、通勤に係る費用が削減される一方で、自宅におけるインターネット費用や電気代、設備費など新たなコストが発生する可能性がある。こうした実態を踏まえ、賃金や各種規程の内容を見直すことが望ましい。
なお、賃金は労働契約書における必須記載事項の一つであるため、雇用者が賃金の変更を行う場合には、労働者の同意を得る必要があり、一方的な変更は認められない。
・労働時間管理:時間単位で勤務する労働者に対しては、柔軟な働き方が導入されている場合であっても、通常の労働時間や休憩時間について労働契約書に明確に定め、労働者が自身の勤務時間に関する責任と義務を十分に認識できるようにする必要がある。併せて、雇用者はオンライン勤怠管理システムやパフォーマンス管理ツールを導入することで、勤務時間を適切に把握・管理し、賃金計算の根拠を明確にしておくことが望ましい。
1.2. フリーランス
現行法において「フリーランス」という働き方は明確に定義されていないが、一般的には、時間的・地理的な拘束を受けず、成果物に応じた報酬を受け取る独立した働き方を指す。
実務上、多くの雇用者はフリーランサーとの間で労働契約書を締結するのではなく、「業務委託契約」「請負契約」「サービス契約書」などの形式を採用することが多い。ただし、契約の内容において、報酬の支払い、賃金としての性質、一方当事者による業務の管理・指揮・監督に関する定めが含まれる場合、契約の名称にかかわらず、実質的に労働契約とみなされる可能性がある。このような場合には、雇用者に対して社会保険料の追徴、行政処分、さらには労働契約の締結義務や社会保険加入義務、退職手当の支払い義務など、労働法上の責任が課されるリスクがあるため、十分な注意が必要である。
2. 電子労働契約
労働法第14条第1項により、労働契約はデータメッセージ形式による電子的方法を通じて締結することが可能であり、書面による契約と同等の法的効力を有することが定められている。
したがって、電子労働契約は、法令に従って適切に作成・締結されていれば、書面による契約と同様に法的効力を持つ。近年のデジタルトランスフォーメーションの加速やテクノロジーの進展により、電子契約の導入は今後ますます増加し、不可逆的な流れとなりつつある。電子労働契約を導入することで、契約締結や保管にかかる時間やコスト(印刷費・保管費など)を削減できるほか、社内システム上での一元管理や検索の利便性が向上し、リモートワークにおける遠隔締結にも対応しやすくなる。
もっとも、電子労働契約を実際に法的効力のあるものとして運用するためには、電子取引に関する法令を遵守する必要がある。特に、電子署名(トークン)を用いる場合には、電子署名認証サービス事業者が発行する認証書に基づく電子署名を使用することが求められる。
3. 営業秘密・技術秘密の保護条項および個人情報保護条項
営業秘密・技術秘密の保護条項
オンライン業務環境の一般化やAI技術の普及に伴い、情報セキュリティは企業の存続に直結する重要課題となっている。特に、コンサルティング、IT、金融、クリエイティブ分野などにおいては、戦略情報、顧客データ、パートナー情報、知的財産などが漏洩した場合、企業に甚大な被害をもたらす可能性がある。
このような背景を踏まえ、営業秘密・技術秘密に関与する労働者に対しては、秘密保持の内容、期間、違反時の対応などを明記した条項を労働契約書に盛り込むことが望ましい。これらの条項は、労働契約書内の一条項として規定することもできるほか、付属文書として添付する方法、あるいは別途労働者と個別に契約を締結する方法でも対応可能である。
実務上、多くの雇用者は、労働者と「情報秘密保持契約(英語では “Non-Disclosure Agreement” または “NDA”)」と呼ばれる独立した契約書を別途締結する方法を採用している。
秘密保持義務を労働契約内に規定することで、書類作成の手間を軽減できる一方、労働契約終了と同時に当該義務の効力が消滅するリスクがある。これに対し、NDAを労働契約とは別個の契約として締結すれば、退職後も一定期間にわたり秘密保持義務を継続させることが可能となる。
個人情報保護条項
労働者は、労働関係の開始時または雇用期間中に、氏名、生年月日、性別、住所、学歴、健康状態などの個人情報を雇用者に提供する義務を負う。
近年、ベトナムでは個人情報保護の重要性が高まっており、その姿勢は、個人情報保護に関する政令第13/2023/ND-CP号をはじめ、策定中の個人情報保護法案やサイバーセキュリティ法などの関連法令に反映されている。
したがって、雇用者が労働契約の締結や雇用関係の履行にあたり、労働者の個人情報を取り扱う場合(収集・保存・処理等)には、関連法令に基づく義務を適切に履行する必要がある。具体的には、個人情報の処理に先立ち、労働者から同意を得るための「個人情報処理に関する同意書」を締結し、その中で処理の対象となる情報や処理目的を明確にすることが求められる。この同意書は、労働契約書の一条項または付属文書(別紙)として規定することもできるほか、労働者との間で別途、個別契約として締結することも可能である。
こうした対応を行うことで、関連法令の遵守を徹底するとともに、法的リスクを最小限に抑え、透明性の確保と労働者の権利保護を推進することができる。
おわりに
リモートワークやフリーランスといった新たな働き方の広がりや、電子契約の普及に対応するためには、労働契約書の内容を現状に即した形で見直すことが重要である。あわせて、情報セキュリティや個人情報保護に関する条項も強化し、デジタル時代におけるさまざまなリスクへの備えを講じる必要がある。これらの取り組みは、法令遵守を徹底するだけでなく、企業の信頼性向上と持続的な成長を支える基盤にもなりうる。
参考文献:
・2019年労働法
・2023年電子取引法
・政令第13/2023/ND-CP号